ヒートガードを検討する
荷台右側へのカバン装着に向けて
ロードホッパーの荷台右側へのカバン装着は失敗が続いています。スポーツスリムサイドバッグ.040(RSタイチ)は、九州ツーリングもこなしてくれましたが、道中でカバンの底がマフラー(サイレンサー)に付いて穴が開きました。これを避けるために接続ベルトを強く締めるとベルト自体が抜けてしまいました。
続いて導入したNB-92-BK 防水サイドバッグ(デグナー)もまた、2019年11月16日のBikeJIN Camp Meeting@西湖へ行く際に、車体右後方に装着したところ、カバンの底がマフラーに当たって布地が溶けて穴が開いてしまいました。
やはり根本的な問題はマフラーがカバンの布地を溶かしてしまうほどの高温になることに尽きますので、触れても溶けないような対策こそが本筋です。防水サイドバッグ(デグナー)の化繊布地が溶けてマフラーにこびり付き、見栄えを著しく損ねていますから、これを隠すカバーを兼ねて、マフラーにヒートガードを取り付ける方法を考えました。

化繊が溶けて付いちゃった
ネットを流れてマフラーに装着するヒートガードについて調べると、デイトナやモーターヘッドなど、いろんなメーカーから発売されており、これらの商品は、サイレンサーをパイプバンドで止める方法をとっているようです。
ページワン春日部へ半年点検の予約で電話を掛けた時にあわせて相談したところ、やはり化繊が溶けるほど熱くなります。マフラーに留める金属バンドが熱を伝えてしまうんです。熱くならないところからステーを取り出せると良いんですがとのアドバイスを貰いました。
そんな中、パインバレーというショップのサイトで超断熱 フレキシブルヒートシールド(Design Engineering)のテストの様子を動画で紹介していました。金属バンドで固定する方法は同じですが、100℃くらいまで温度が下がっています。焼く程ではなく煮る程度まで下げてくれるなら、カバン側で対応できる手が見つかるかも知れません。
12月7日、ページワン春日部で半年点検をお願いしますが、一番最初に話したのは溶けてこびり付いた化繊を取る方法を教えて下さいでした(泣)。
続いて針替さんに上記動画を見て貰って、ヒートガードを装着できるか相談したところ、取り寄せてもらうことになり、点検と合わせて取付作業をお伺いする段取りとしました。
12月15日に引き取りに行くと、溶けた化繊生地のこびり付きを取ってマフラーを綺麗にして貰っていました。ありがたいです。

綺麗になりました

ヒートガード
取り寄せてもらったヒートガードを見ると、固定用の足が出ていて、これでヒートガードがマフラーから離れることで熱の伝わり方を軽減させるはずです。

ここにバンドを通します
ところが、付属のパイプバンドが小さくて、マフラーに取り付けることができません。ページワンで準備できる取付用金具は取り付けてしまうと外せない(金属バンドを切るしかない:再利用不可)ものでしたので、結局、取り付けずにカバンに入れて持ち帰ることにしました。
というのも、ヒートガードは普段外しておいて右サイドバッグを使う時だけ付けたいのです。こういうパーツは一度付けたら付けっぱなしが一般的ですが、右側のサイドバッグが絶対に必要!と思う機会は少なくて、一年に2~3回程度です。必要に応じて逐一脱着するのは手間で面倒ですが、極力余分な部品が付いていないのがロードホッパーの魅力だと思っています。
そんなわけで、後日取り付けに向けて再始動しました。取付用パイプバンドを別途調達するため、まずはマフラーの取り付け予定箇所の円周を測ると約30cm、バンドを通すヒートガード側の足の幅を測ると13~14mmでした。あまり狭すぎてもズレるので近いものを。
結果、径100mm程度を取り付け可能な長さがある、幅13mm程度のベルトを使ったパイプバンドが必要です。ドイト戸田店に行ってフラフラ歩いてみると、ちょうど良さそうなものがありました。オールステンレスクリップ12幅 90-110(ノルマ)です。1個で400円を切る程度だったはずです。

排気管固定用バンドらしいです
パイプバンドのベルトにヒートガードを通して、マフラーに巻いて締め込んでやれば完成ですが、そのまま付けたらマフラーに傷が付きそうです。そこでシートカバー 保護・遮熱シート 耐熱 BTG4501(X-EUROPE)を、ベルトの幅12mmに合わせて細長く切って、内側に貼って傷予防とします。
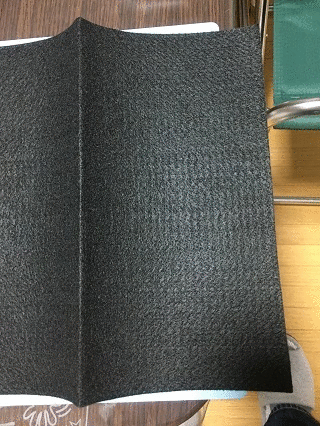
こんなシートです
マフラーの外周の長さ300mmより若干短い290mmに2本切り出して貼り付けました。この商品は裏地がテープになっています。
さらにヒートガードの足の底面、マフラー表面に押し付ける部分にも保護・遮熱シートを切って貼り付けます。

足の裏です
1月13日に装着テストをしてみました。ヒートガートの足に取り付けバンドを通します。

こうして準備して…
見たところ、そんなに不格好でもないな…このまま着けっぱなしでも悪くないかも?と思いますね。
ここまで準備をしたのですが、春になってコロナウィルスの影響でバイクで走る機会が失われ、さらに半年が経ち、法定点検の時期がやってきました。2020年5月30日、ページワン春日部へ向かう際に、ヒートガードを装着して、走行テストを行います。

ページワン春日部に到着
温度計を持ってページワン春日部まで走り、到着するやエンジンを止めずにヒートガードの表面温度を測定してみます。

80℃超ってトコか
およそ80℃を超えたあたりで頭打ちになりました。もちろん素手で触ると火傷する温度には違いありませんが、これくらいの温度であれば、焦げない溶けない布地のカバンがあるんじゃないかしら…?と期待してしまいます。
ヒートガードを取り寄せて貰ってからずいぶんと日が空いてしまいましたが、テスト結果を伝えられてよかったです。これでショップのノウハウの一つになれば、依頼を受けた甲斐もあった、と思って貰えるかも知れません。
翌31日(土)点検を終えたとの連絡を受け、引取って帰宅しました。バイクを車庫に入れる前に、ヒートガードを付けていない部分の温度を測ったのですが、200℃を超えたところでやめました。この温度計は260℃まで計測できますが、200℃だろうが260℃だろうが、手を付けられない高温だってことだけは分かりました(苦笑)。
マフラーおよびヒートガードはまだ熱いので、ヒートガードを着けたままバイクを格納してしまいます。無理して外そうとすると火傷のもとです。工具を車庫に保管し、マフラーが充分に冷めた後、あるいは次回出発する際にヒートガードを外す運用にします。出発までに時間が掛かっちゃうけど(笑)。
ただ今後、やっぱり逐一取り外すのは面倒と付けっぱなしになるかも知れませんね(笑)
Copyright (C) びぃ,2020-06-08,All-Rights Reserved.

